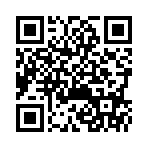› 笑う門にはふじぶー来る › 2010年01月20日
› 笑う門にはふじぶー来る › 2010年01月20日2010年01月20日
恵比寿祭り
昨日、いつものように仕事で大川まで
30年お世話になっている取引先の大欣木工㈱の会長さんから頂いた鮒の甘露煮
一般的に「家具の街大川」と言われていますが、家具の産業は工場・資材・機械・運送・卸業含めて
近隣の筑後・久留米・佐賀・柳川まで大きく広がっています。
大欣木工㈱さんも柳川にあります
会長さんは奥様共々とても研究熱心なかたで、自らの手で作ってきた技のある職人さん「匠」です
どうして今日、鮒の甘露煮をいただいたのか・・・
元来、1月20日(二十日正月)は、恵比寿祭りで、古来、恵比寿様は商売の神様として特に商家の尊信を得て、当日(20日)は、その像を祀り商売繁盛を祈祝した。
この風習は、やがて商人のみでなく、地主が小作人を御馳走して日ごろの労苦を慰労する日とまで広がり、更に一般社会庶民階級にまで波及し、近親知人を招き一家の繁栄を祝福する日と拡大して庶民の伝統祭事となった。
もともと恵比寿様の御馳走の中心となすものは鯛であったが、当時鯛は非常に高価で庶民には容易に得られなかった。そこで、鯛の代わりに、鯛によく似た魚で然も容易に庶民に得られる鮒が多く用いられるようになったと伝えられている。
1月20日の恵比寿祭り(二十日正月)は、どこの家でも一年を代表するご馳走をして祭るものである。
その前日(1月19日)に鮒市が立つ。
この鮒は、遠く柳川、佐賀平野、白石地方のクリークからとった鮒を持って朝早くから集まってくる。
それを目掛けて地元は言うに及ばす、近郊在住から鮒を買いに集まってくるのである。
それぞれ買い求めた鮒は、一々昆布で巻いて頭から骨まで食べられるように夜更けまで煮る。
その時大根、牛蒡、人参等大きく切って煮詰めるのである。翌日(1月20日)は、恵比寿大黒を床の間に飾って鮒の外に作った御馳走を所狭しに並べ、家族そろっていただく。
浜町を中心とする人々にとって「二十日正月」は、正規の正月とは、また別の楽しみであり、喜びである。
鹿島市資料より
と、いう訳でした。
とても美味しくいただきました。ご馳走さまでした
 焼酎飲みすぎました
焼酎飲みすぎました